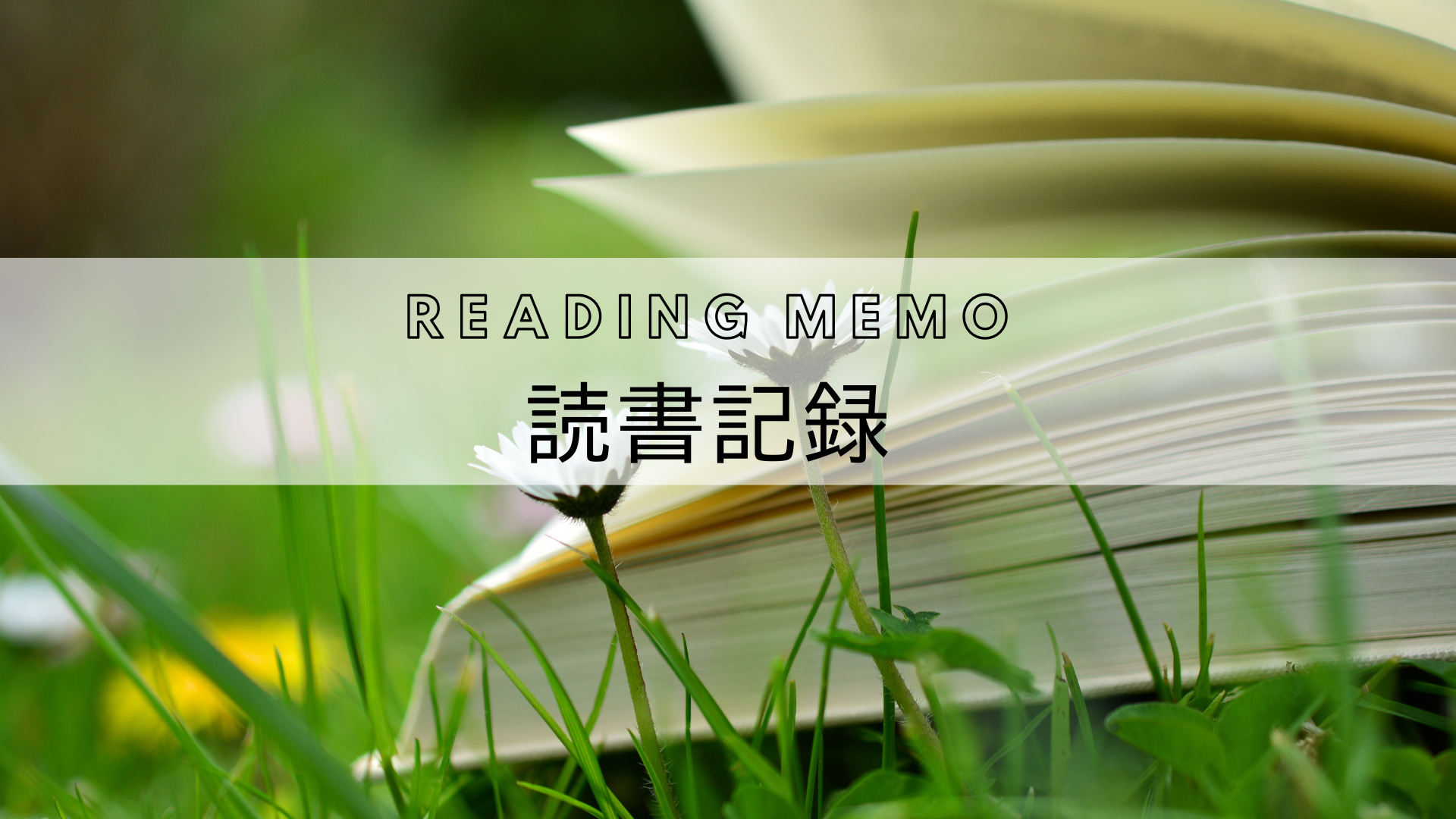ずっと興味のあったラテン語。
このラテン語を教えてくれるという教書は、やはり語学教書からでの発行しかないのは当然。ただラテン語を知って何をしたいのかを考えた時、もはや会話をしたいという希望よりも、欧州の教会などを訪れた時に簡単にでもわかればいいなぐらいの程度でした。そんな便利な本なんてないなと思ってた時に『教養としてのラテン語の授業』に出会いました。
さて、早速の読書ノートです。
あらすじは大学でのラテン語授業シラバス的な流れ
バチカン裁判所で弁護士の資格を所持し、現在は韓国の大学でラテン語についての授業を行う先生が、イタリア(バチカンを中心とするローマ)滞在中に学んできたラテン語と、その授業の時に学んだラテン語周りの事例をもとに記されています。
ラテン語周りの事例というのは、ラテン語が盛んであった古代ローマ時代の賢人たちの背景や哲学者たちの思いなどを整理づけて言葉を教えてくれる内容。なので印象深くフレーズと向き合うことができます。
こと現在でも語られる有名な句は以下でしょうか。
「Do ut des (与えよ、されば与えられん)」
「Hodie mihi, Cras tibi(今日は私へ、明日はあなたへ)」
「Quae sunt Caesari et quae sunt Dei Deo(カエサルのものはカエサルに、神のものは神に返しなさい)」
このように有名なラテン語での言い回しが章のタイトルとなっており、そのテーマ性に合わせて記されています。大学の先生だけに、各課題に基づく論証なのでシラバス的なような感じでしょうか。最終章にきちんと締まりをつけてくるのもまさに大学で講義を聞いているような感じになります。
ラテン語入門者のための授業が一冊の本になったような。
ラテン語の根本性を理解すると面白い
ラテン語ベースで理解をして読み進めるととても面白いです。ことローマ人の背景や語り継がれるフレーズの本当の意味とか、真理だなと心に落ちます。著書のいう「Obedire Veritati!(真理に服従せよ)」というところでしょうか。やはりバチカンで学んでいらした先生の著書なので、かなりカトリック的な見解もあります。宗教的な背景があってのローマ時代と、そのカトリックを支持する国々の派生言語から垣間見ると、その根底なるものがわかってはきます。かなり抽象的なログ記録ですね。
私は英語はテンでダメですが、イタリア語を学習してきたので、通訳翻訳はできる方です。そしてイタリア語はスペイン語に並び、ラテン語の原型に近いともされているために、言語のルーツをわかることができました。そしてその背景も良く理解できます。同時にラテン語はかなりのワードが英語にも派生しているので、英単語ベースでも言葉の理解ができると思います。意外とひとつのワードであったとしても、組み合わせでできていて、その組み合わせになるには背景があるということを知ることができます。
あ!やっぱりラテン語と英語って似ているね! ではなくて、そういう理屈があったんだという完全理解へ導いてくれることでしょう。
なので、ラテン語とはいえども、得て不得手関係なく語学に興味ある方すべてにおすすめできる著書といえます。 同時に内容は言語学というか、生き方への調べとも言える教訓みたいなのが満載なので、自己啓発及び自己を癒すなどの時にもお勧めしたい著書でもあります。
後付けの言葉が重く響く
読み進めるうちに気になる方もいらっしゃると思います。
同時に筆者が韓国人であることを気にされる方もいらっしゃるかと思います。
そう。やはり筆者が韓国人であり、日本語訳の読み手は日本人であるために、若干の理解背景の違和感は否めないかと思います。
その違和感は監訳者あとがきの東大名誉教授の木村凌二氏の言葉によって救われると思います。
引用本書275ページ
やはり否めない文化の違いから生まれる相対性なので、本書の記す教養としてのラテン語の原則に集中すればとても楽しい著書であると言えるでしょう。
正直、その違和感のある表現を残しながら翻訳して出版したということはすごいなとは思いましたが、ダイバーシティな時代にも入っているということですね。
今も語り継がれる意味を知る
最初に記載した通り、ラテン語では有名な言い回し。大切なポイントは、日本語にもなって、映画にもなって、今この21世紀にも使用されるフレーズはローマ時代から使い続けられているということではないかと思います。それはすべて真理であり、人は結局のところ何世紀に渡っても人であることを再認識させられます。
なので、今まさに悩んでいることや途方に暮れていることも、このシンプルなフレーズによって解決されてしまうという。そして何世紀にも渡って、人間という生き物がぶつかる悩みというのは一律なのではないかとも思うようになります。
ゆえ、とてもこの著書を読み終わった後に心が軽くなりました。
ちょうど最近に嫌なことが立て続けにあり、どのように理解して前進していくかを日々問答していましたが、自己に解いても禅問答。そういう禅問答な自分に一矢撃ち抜く感じと言いますか、目の前の光陰が開けてきます。
人間に備わっている感情の喜怒哀楽。
人間の限られた時間という生死。
人間の生きる関わりとなる他人という家族、友人、同僚。
人間の生きる糧を得るための仕事。
この全てが万事順調なことは相当だと思います。
なのでラテン語を勉強するというのではなくて、少し躓いた時に開いても良い著書なのではないかと思います。
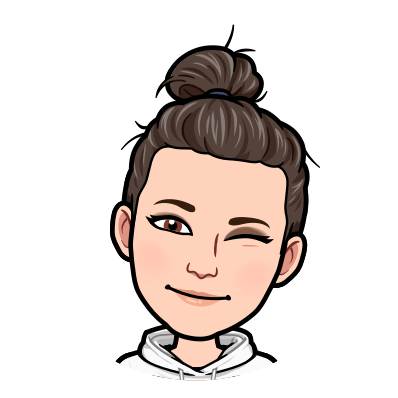
ラテン語を勉強したくなりましたか?