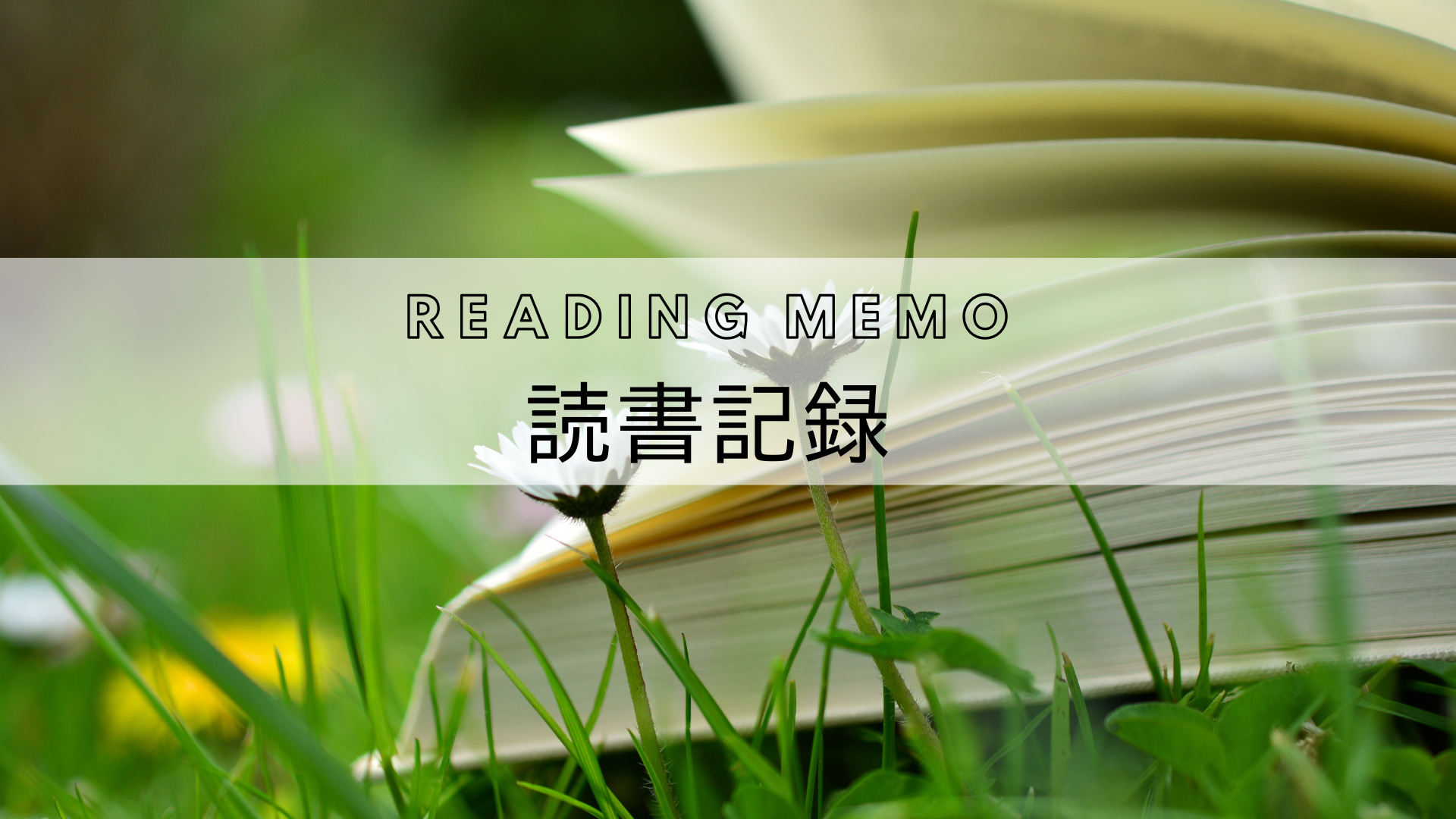赤帯で「2021年一番売れた本」と書かれていれば手に取らないはずがないですよね! と思いきや、実は知人に面白かったと紹介されて手に取った事実です。そこはなぜか重い腰でした。というのはタイトルで容易に内容が想像できてしまったからです。
まぁ、いわゆる世間一般的に言われる「スマホばかりしないで!」みたいな感じでしょうか。
精神科医が具体的に著作で紐解く『スマホ脳』
著者はスウェーデンの精神科医であるゆえ、医学的な根拠の元にスマホ脳がどのように形成されていくかを論じています。
まずスマホがなかった古代の人間を人類としての本質的な基本行動を描くことから始まります。そもそも人間自体の人的機能は何千年経てども変わらずなのだが、文化の発展発達とともに周りの環境は日進月歩と変わっていく。その変化の中でスマホが登場したことによって、どのように人間が変わってしまったかというのを紐解いています。
それは脳にある扁桃体に作用するものや、ドーパミンによる人間の常習性が利用されたり、さらに言えばメンタルヘルスの問題を引き起こし、結果的には人類は進化しているのか退化しているのかという問いに迫っていきます。
スマホの登場から利用されるSNSが引き起こす社会問題。うつ病などの精神疾患などもスマホ起因が増えているが、なぜ増えてしまったのかなども具体的に医学的見地から解説しています。
そういった理由から、IT企業トップは子供にスマホを与えないだとか、社会問題としてキレやすい人が増加するのも、私たちのIQの低下も見受けられると展開されていきます。
21世紀に欠かせないスマホとの共存方法
「スティーブ・ジョブズは我が子になぜiPadを触らせなかったのか?」 というのは、パラドックス的な命題です。だってスマホを作った張本人が、なぜ自らの作品であるiPadをお父さんの仕事として与えないかという。
それはスマホはあくまでもその利益を生むツールであって、彼らはそこに潜むリスクの責任はないのです。なのでリスクがわかるからこそ、自らの子供には与えなかったという理論がわかります。頭ではわかっているけど、なぜどうしていけないのだろうか? ということが腑に落ちてきます。
同時に、もはや現時代において、スマホがないと仕事にならないことや、生活インフラが断念される方もいるでしょう。なので、正しいスマホの使い方へ導いてくれる教科書のような書籍です。
そして手書きでものを書く大切さなどもだんだんわかってくるようになります。
SNSによる社会問題の俯瞰
Facebook、Twitter、Instagram、Note、TickTok、Youtubeなどなど。
スマホやパソコンをインフラとしたSNSは増加し、そこで非接触のコミュニティが不変となっている現代において、社会問題もまた不変になる不幸があります。
SNSで「いいね!」がつかないだけで落ち込んだり、フェイクニュースに踊らされたり、混乱させられたり、他人の投稿が気になってしまったりすることはありませんか?
それが社会問題にまで発展して自信を失わせたり、嫉妬などを引き起こしたり、スマホがないとイライラするようになったり、自分で考えて解決することが困難になってきたりします。
テクノロジーが発展して高度化する中、人間だけがこのままだと退化してしまう危険性をはらむのは、脳の仕組みの組み替えがスマホの使用次第ではエラーを発生させるからだと私は本書を読んで理解しました。
スマホとの正しい関係性
子供にスマホを与えてはいけないというのは、わかっている親が多いと思います。
でもそれがどうして本当にいけないのかがわからないという観念的な感じです。
そして、子供はダメだけど大人はいいという矛盾もなぜなのでしょうか?
そういうイメージ的ないい悪いではなく、やっぱりPC同様スマホもツールに過ぎないという感覚を持つことが大切です。
スマホ依存症の方は、自覚症状ない人が多いと思うので、良書といえど、本当に読んで欲しい人には伝わらない気がしたのが残念なところです。
私もこのオフスタのブログやツイッターなどを改めてはじめて、他人のことやいいねの数などを気にせず、自分のツールとしての忘備録に割り切った時、物事が自由に描けるようになりました。
そして、読んでみたい著者の『一流の頭脳』ですが、日本では入手困難。
『運動脳』も続けて読みましょうか。
これもなんとなく書きたいことはわかりますが、理論的に知りたくなりました。