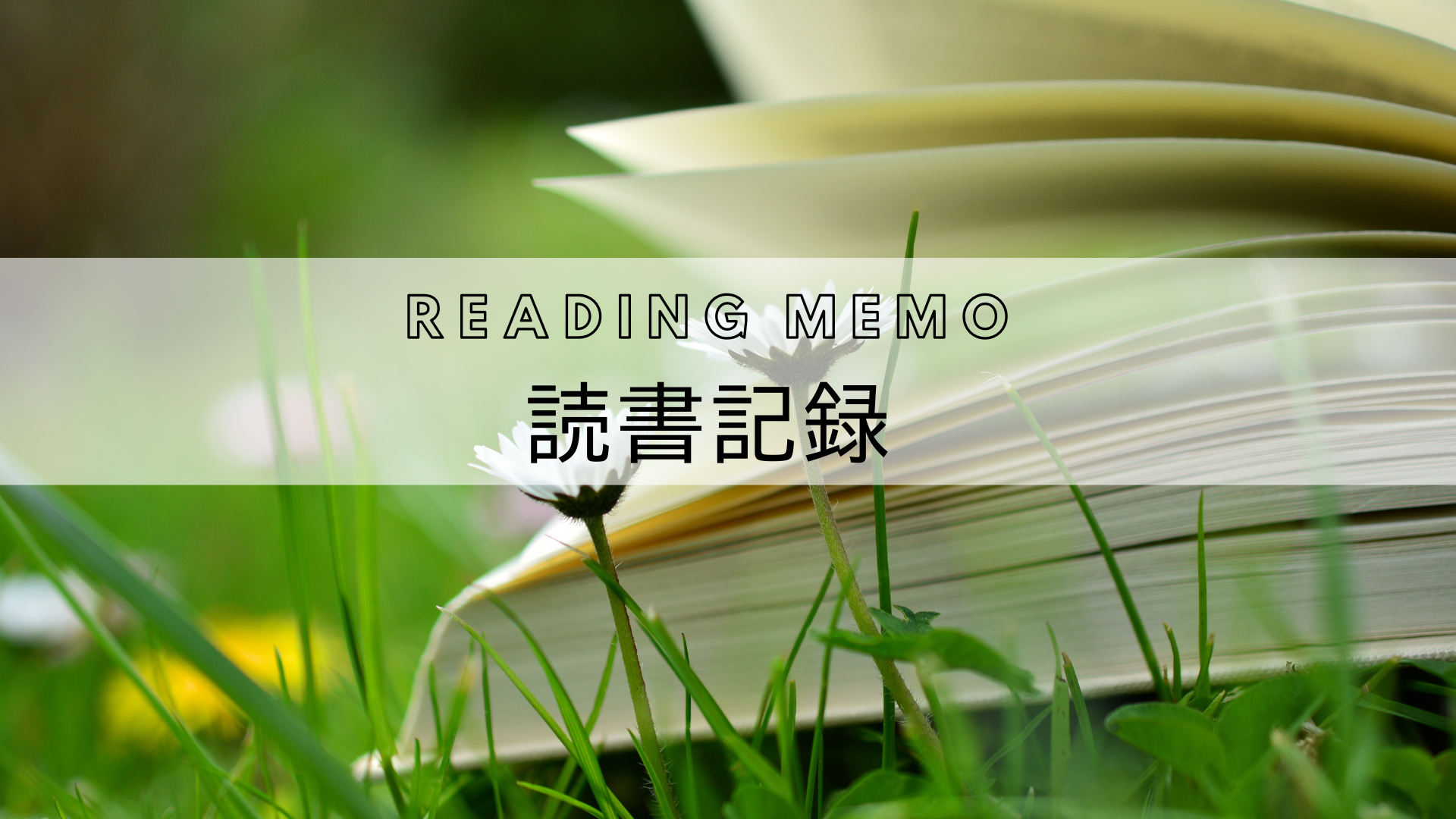よく行く本屋さんの棚のエンドにおすすめ本としてあったものの、なかなか手が伸びませんでした。でも随分と長くエンドにあったので、おそらく相当面白いんだろうと思って購入を決断。案の定、すごく面白かったです。本屋さんのオススメにはできるだけ従おうと確信しましたのは、この書籍を読了した日でした。
ということで読み終えました國分功一郎著『暇と退屈の倫理学』です。
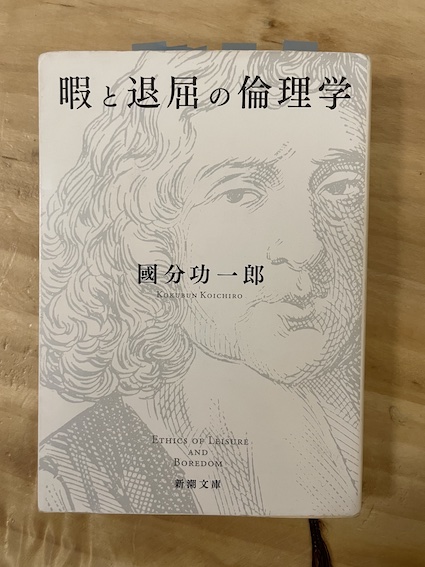
付箋をいっぱいつけることとなった『暇と退屈の倫理学』國分功一郎著
ウサギ狩りの目的はなにか?
確実なのはタイトルの通り「暇と退屈」というある種の状態を徹底分析した書籍です。最初のウサギ狩りの例え話などは、してやられた感なる納得がありました。
そんな仮に興じる人たちについてパスカルはこんな意地悪なことを考える。ウサギ狩りに行く人がいたらこうしてみなさい。「うさぎを狩に行くのかい? それならこれやるよ」。そう言って、ウサギを手渡すのだ。
(中略)
なぜウサギ狩りにいこうとする人は、お目当てのウサギを手に入れたというのに、イヤな顔をするのだろうか? 本文抜粋44ページより
ここで猟をするということが職業の場合は糧になるかもしれなが、趣味になる場合は暇と退屈の潰しというものになるのだなぁと感心しました。こういう例題が出てくるので、出だしから楽しい始まりの本書でした。
”暇と退屈”は貴族の特権だった。
そしてその暇と退屈は高貴な人々の特権であったという。これを読んだ瞬間に思い浮かんだのは、私の稚拙な読了記録からオスカーワイルド著『ドリアングレイの肖像』を思い出しました。まさに背徳な生活のなか快楽を生きるヘンリー卿のお戯れが描かれ、それに翻弄された少年ドリアンの物語。
そして『ドリアングレイの肖像』に導かれるのであれば、原田マハ著の『サロメ』も欠かせません。この『サロメ』もまた、暇と退屈により翻弄されたピアズリーの不幸が描かれていますが、何はともあれ、そこから導かれる美術史の真実。実際はフィクションなのですが、その作品に触れたくなるような文章構成をも思い出しました。
廃退的な貴族世界の物語がお好きな方は、その有閑な暇つぶしの理由がこの著書で解き明かされること請け合いです。
そういう意味では、ジェイン オースティン著『偏見と高慢』も該当するかもしれません。
自分の現実を思い知る映画『ファイトクラブ』。
今となっては格闘技のブレイキングダウンの方が知名度的には高いと思いますが、この書においてはブラッドピット主演映画『ファイトクラブ』でしょう。まさかこの映画が引き合いに出されるとは思いませんでしたが、この映画の登場により、とても内容が腑に落ちてきます。その後、消費社会が暇と退屈から生産される社会であるということを畳み込むように展開する著者の解釈の折り返しがまた素晴らしいので、ここは飲み込まれるように読み進めていただきたいところです。
感覚で習慣性を知る環世界と人間の比較。
ここはちょっと人間的ではない比較だったので、なかなかしっくりというか、重い足取りになった読書ペースでした。せめて哺乳類との比較だったら良いのですが、ダニとかハチとか。確かに動物という概念では人間と一緒なのでしょうが。なので、私はこの章において、自らが暇と退屈の倫理学のまさに渦中の実験台になっているかのような気持ちになります。そして既に読んだ章”暇と退屈の哲学”で導き出される「何かに際して退屈すること」という退屈の第二形式の状態を経験できます。人によると思いますが、私はこの章の足取りが少し重かったです。でも面白いダニやハチやトカゲの事実を端的に知ることができたので、気晴らしにはなっているのかもしれませんが。
哲学を知っているような気持ちになれる。
哲学を元にした考察の小説。小説ではなく著書ですね。それも気づきの考察というものなのか、人間の根本的な習性を俯瞰して理論的に解釈解明していくような。いかんせん、とても頭のいい文章です。そりゃ東大の教授が執筆しているわけで、当然のことなのですが。なので、ある程度の哲学的基礎知識がないと難しいところもありますが、さすがだなというところは、理解させるという意味での文章構成が最高です。なので全く哲学がわからなくても、その登場人物やその思想に興味をもたせ、この著書を読み終わったら、早速にでも手をつけてみようかなという気持ちにもなります。
理解させる前提の文章構成が素晴らしい。
章ではなく節の区切りが実に端的なので、理解ごとに区切っているところにすばらしさを感じました。難しいことを書いているようでありながら、実はとても単純なことだったりします。そして哲学的な専門用語で凝り固まっているわけでもなく、非常にスムーズに理解できます。濃度が高い文章になってはいますが、短い節がとても助かります。ざっと読み込むというよりも、節ごとに読み進めても良いと思うので、ライトノベルなどと併読すると、読書習慣を進める上では楽しめると思います。その場合は、この著書をオンにして、ライトノベルがオフになるかもしれませんが。
利口になれるお得な著書です。
また読書の枠が広がりそうな著書でした。何を読もうか悩み、人生において時間の使い方やオフスタイルの口実を語り続ける私ではないですが、暇な時間というのをどのように有効に使うかなどを思う人にはオススメです。
とくに結論の章に辿り着き、その倫理学的な結論に導かれた時、なるほどこういう学習ができたのかと確信できる心理状態に至りました。実に不思議な感覚です。もちろん読み手によってその感覚は異なるかもしれませんが、ある一定の暇と退屈からの産物を得られているとは思います。暇と退屈は混沌でありながらも、人間にも信義的リチュアル(儀式)を繰り返しながらもルーティン(習慣)にすることに、決断という意義があると考えました。
ライトノベルや物語小説というわけではないので、サラッとした読書が好きな方にはお勧めはしませんが、先にも記載した通り、併読して読み進めると、ちょっと利口になった気持ちになります。そういう意味ではお得な著書かもしれません。読書ノートの記録にも、ちょっと知的な自分がいるかもです。ジャーナリングでもいいですね。
そして最後にコロナやインフレーションで、今までの生活に急速にブレーキがかかり、我慢を余儀なくされる方々もいると思います。そういう中、暇と退屈ができてしまったという状況にある人には是非ともおすすめしたい本書です。私はこの書を読んで、暇と退屈を利用してオフスタイルを充実させていこうと思うようになりましたから。